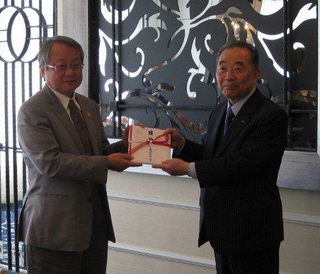会報ねじ 新着記事
- 製造業の海外移転を考える(野口先生のブログから)
-
野口悠紀雄先生のコラム「震災復興とグローバル経済――日本の選択」がシリーズでブログに掲載されています。未来開発パブリシティ委員会の関心事の一つに「海外動向」があがっています。その参考として情報提供させていただきます。
・ 産業構造は、継続的な円高、震災による国内生産条件の変化で大きく変わった。これらは構造的な変化で、経済に対する考え方、政策のあり方も見直すべきだ。
・ 海外生産比率は、特に機械産業において顕著な増加があったが、進出企業の戦略は、現地の需要に対応しようとするものが多い。
・ この結果アジアにおいては、日本の製造業は、海外生産で安い労働力を使って安いものを作り、結果として低価格競争に巻き込まれて行かざるを得ない。このような従来型の海外生産は製造業を衰退させる。
・ 今後は、アジア新興国の需要に対応するよりは、日本の需要に応えることを目的とすべきであり、エネルギー消費の大きな産業を移転すべきだ。
などなど、興味深い提言がみられます。あくまで、経済学の立場、マクロな立場からの視点ですが、それらを参考にしつつ、企業の立場からは、それぞれにとっての戦略的な意味(進出目的)を明確にしてゆくことが大事だと思います。
尚、掲載されているURLを最後に紹介いたしますが、シリーズで大変長いものです。以下、日本企業の海外移転に関係する部分をサマリーさせていただいたので、参考にしていただければ幸いです。
【以下サマリー】―――――――――――――――――――――――――――東日本大震災によって日本経済の条件は大きく変わった。4月以降の貿易収支の大幅な赤字化、震災による国内生産条件の悪化などである。企業(特に大企業)の生産拠点の海外移転の動きは円高によるものだが、生産条件の変化に対応していっそう加速するであろう。電力供給の不確実性、電力料金の上昇、復興投資による金利上昇などによって、国内での生産や投資はますます不利になる。これらの変化を受け止め、経済に対する考え方を大きく変える必要がある。
(1) 国内の産業構造を、これまでと同じものに維持する必要はない。大震災で日本の比較優位は大きく変わったので、この機会に産業構造を大きく変えるべきだ。企業はすでに生産拠点の海外移転を進めているので、それを押しとどめてはならない。雇用創出は、国内に新しい産業を作ることによって行うべきだ。
(2) 新しい産業によって脱工業化が進めば、電力需要も減る。それでも電力が不足するのであれば、無理して火力発電へシフトするのでなく、製品輸入を増やすべきだ。これは、外国の電気を間接的に購入することを意味する。
(3) 新しい産業を興す場合、日本人だけを雇用しようとするのでなく、外国人専門家の活用を考えるべきだ。
(4) 復興財源に関しても、日本が保有する巨額の対外資産の活用を考えるべきだ。国際収支においては、貿易収支の黒字化をめざすのではなく、所得収支の黒字拡大をめざす必要がある。
これらの方向付けは、そもそも震災以前から必要とされていたものだ。つまり、震災による変化は、進むべき方向を変えたのではなく、その方向を選択する必要性を強めたのである。
海外生産比率の増加についても、構造的な変化を見る視点が必要である。
海外生産比率は、機械産業、とりわけ、情報通信機器(26・1%)、輸送機器(39・3%)において高い水準になっている(数字はいずれも国内法人ベース)。大企業によって行われている組立型の生産活動は、すでにかなりの程度、海外に移ったことがわかる。
自動車について企業別に海外生産比率を見ると、ホンダ72・9%、日産71・6%、スズキ61・5%、トヨタ55・9%と、生産の過半は海外で行われている。OEM(相手先ブランドによる生産)メーカーやファウンドリー(半導体チップの生産工場)への委託による海外生産を含めると日本製造業の実態的な海外生産は、上の数字以上に進んでいると考えることができる。
日本企業の海外移転は、リーマンショックによる経済危機までの10年間中断していた。昨年夏ごろから生じている海外移転は、つまり、この10年間の円安バブルによって一時的に中断されていた動きが再開しただけのことである。それまでは円安が続いていたので、外国から見た日本の賃金は低く抑えられていた。そのため、海外移転の必要性は緊急の課題ではなかった。しかし経済危機後に円高が進み、ドルで評価した日本の賃金は上昇した。だから海外生産の有利性が高まった。とりわけ労働力を多用する組み立て型製造業の海外移転が進んでいる。
経済危機によって、国内法人の利益率が急減し、国内生産と海外生産の相対的な関係性が逆転し、海外生産が圧倒的に有利になったのである。需要の減少は世界的だったことを考えれば、国内と海外でこのような利益率の差が生じた大きな原因は円高にあったと考えることができる。
震災以降の今後を展望すると、電力コストの上昇によって、国内の利益率はさらに下がるだろう。そして、それは電力多消費産業である製造業において顕著に生じることだ。だから、移転を阻止するのは不可能だ。それを所与として、国内での雇用創出を目指すしかない。それをいかなる方策で行うかが重要な課題だ。
従来型の海外生産は製造業を衰退させる
製造業だけに限ると、現地法人の従業員はで368万人だ(基本調査」)。ごく最近の数字との関係を見るために「海外現地法人四半期調査」を見ると、10年10~12月で357・1万人だ。これは、日本の製造業の総雇用者1004万人の35・6%であり、かなり高い比率と考えることができる。
進出企業の戦略は、現地の需要に対応しようとするものだ。つまり、「日本人が使うものをアジアの工場でアジアの労働力を用いて生産する」ということではない。日本企業は、安価な労働力を求めているというよりは、安価な需要を求めているのだ。そして、アジアの場合、売れるのは低価格製品が中心で、従業員1人当たりの売り上げは国内の半分と少ない。ただし、低賃金なので国内生産より利益率は高くなる。
これを簡単にいえば、日本の製造業は、海外生産で安い労働力を使って安いものを作り、その結果利益が増加しない。アジア進出は製造業発展のために役立っているとはいえない。このような形態の進出が望ましい形なのか否かには、大いに疑問がある。
本来であれば、高い技術を用いて高品質の製品を製造し、高い付加価値を実現すべきだろう。しかし、現実には、低価格製品の価格競争に巻き込まれていると考えざるをえない。いわば日本製造業の劣化が進行しつつあるのだ。生産性を高めるのでなく、需要だけを追い求めている。日本企業はこれまでも利益を追求するのではなく、量的拡大のみを追い求めることが多かった。それが海外進出にも引き継がれているのだ。
ところで、09年以降の海外進出の円高を背景とした加速、また、大震災による日本経済の条件変化も、新しいタイプの海外進出を促している。こうした変化を反映して、今後の海外進出がこれまでとは異なる性質のものになることを望みたい。特に次の2点が重要だ。
第一は、低価格競争からの脱却だ。これを実現するには、アジア新興国の需要に対応するよりは、日本の需要に応えることを目的とすべきだろう。
第二は、業種が変わることだ。これまでは、海外進出は組立型の機械産業が中心だった。今後は、エネルギー消費の多い装置産業が移転することを望みたい。これは、日本に対する供給基地としての役割を果たし得るだろう。
高価格製品の場合と同じ生産設備を用いて低価格製品を生産すると、固定費は比例的には縮小せず、したがって産出物価値に対する付加価値の比率が低下するのであろう。その意味で、低価格製品は効率の悪い生産なのである。そのため、低賃金国で雇用者報酬を圧縮できても、利益率が高価格製品よりは低下してしまうのだ。それにもかかわらず、現実に売り上げが伸びている地域は、1人当たり売上高が最も低い「その他アジア」である。つまり、日本の製造業は、これまでよりさらに、低価格製品にシフトしつつある。
従来のやり方では、日本の製造業は衰退する。その理由として一般に指摘されているのは、次の3点だ。
(1) 国内雇用が流出する(雇用の量的側面でのマイナス効果)
(2) アジアの低賃金に引かれて日本の賃金も下落する(雇用の質的側面でのマイナス効果)。これは日本の中国化だ。
(3) 製品に差別化特性がなく、価格引き下げ競争に巻き込まれる。
それに加え、ここで述べたように「低価格製品であるため、産出額に対する付加価値率が低下し、低賃金労働を用いても利益率を高められない」という問題があるのだ。
第一は、差別化した製品の生産を増やすことだ。アップルの製品であっても、中国での需要増大が顕著という。しかし、これは薄型テレビなどのような激しい価格競争には巻き込まれにくい製品だ。
第二は、アジアの現地需要を取り込もうとするよりは、これまでの電気器具のOEM生産のように、日本の需要に応えることを考えることだ。
第三は、組み立て型製造業だけでなく、エネルギー多使用型製造業の海外立地を考えることだ。
第四は、製造業だけでなくサービス産業、なかんずく金融の海外進出を考えることである。
これまでは、「ものづくりこそ日本の使命」として、製造業を維持しようとしてきた。しかし、円安政策は製造業の生産を増やしはしたものの、雇用を回復させることはできなかった。そして、経済危機後は、雇用調整助成金によって雇用を支えてきたのだ。それ以降進行した円高と震災後の電力不足によって、こうした政策では雇用を支えきれないことが明らかになっている。
【出展 URL】――――――――――――――――――――――――――――コラム・連載 / 野口悠紀雄の「震災復興とグローバル経済――日本の選択」
http://www.toyokeizai.net/business/column/detail/AC/e69ff988cb31baf438acfb94c3a4927c/
(第9回)製造業の海外移転で300万人の雇用減(1) - 2011/08/08 12:16
http://www.toyokeizai.net/business/column/detail/AC/1bee2ce94765f298b94813b76ee5e3fa/
(第6回)震災後に加速している製造業の海外移転(1) - 2011/07/19 12:13
http://www.toyokeizai.net/business/column/detail/AC/f9df2a48798acd1d3bd2fffbe52d47ac/
(第5回)税制を歪めて減税し海外移転を促進した(1) - 2011/07/11 12:13
http://www.toyokeizai.net/business/column/detail/AC/bc140b5397526cd37cac707f494fdaea/
(第4回)低価格製品シフトは製造業を衰退させる(1) - 2011/07/04 12:18
http://www.toyokeizai.net/business/column/detail/AC/25f4e0a7178117a2fa7ddccc7f407b35/
(第3回)従来型の海外生産は製造業を衰退させる(1) - 2011/06/27 12:13
http://www.toyokeizai.net/business/column/detail/AC/87c7b17661081b6266eebad66838739b/
(第2回)円安で中断していた海外移転が再開した(1) - 2011/06/20 12:13
http://www.toyokeizai.net/business/column/detail/AC/6350599788039b2823f70dc426c814ae/page/2/
(新連載・第1回)条件が変わったのに考え方はもとのまま(1) -2011/06/13 12:03以上
- ねじの模擬検定が開催されました!
-
去る、10月26日、愛知県にて、ねじ製造技能検定実技試験の模擬検定が開催されました。(社)日本ねじ工業協会の資格委員会(委員長 椿省一郎副会長)が目指すねじ製造技能検定制度創設に向けた準備活動の一環で、検定を担当する委員20数名他、40名ほどの関係者が集まり、審査過程の模擬トライアル、審査基準、審査方法などについて点検を行いました。
受験生役の模擬試験を審査する検定委員役の皆さんは、この後、審査基準、審査方法について真剣な討議を重ねていました。検定の実現まで大変な準備作業が予定されていますが、こうして一つ一つの準備作業を乗り越え、運営ノウハウのみならず、人を育てるノウハウが蓄積して行くことを実感しました。
(日本ねじ工業協会事務局) - 中小企業施策、助成金(サポインに見る施策の活用状況)
-
【メルマガ ねじ未来開発・パブリシティ委員会ニュース】 2011年9月6日号にて、中小企業施策・助成金のことを取り上げました。
現在、委員会では協会の会員企業様の関心が高いと思われるコンテンツをどのように作成し、デジタル配信して行くか検討を進めています。委員が掲げた関心の高い記事・コンテンツにはどんなものかについては、別の機会にご報告させていただきますが、その中に、「中小企業施策・助成金の活用」というテーマがありました。
例えば、サポイン(戦略的基盤技術高度化支援事業)という施策があります。その申請、採択件数の推移をみると、ねじが関わる「部材の結合」分野は、全20分野の平均を大きく下回り、19位と低迷しています。せっかくの中小企業施策、助成金事業ですから、活用促進の視点はないものかと思います。
このような状況の下、助成金コンサルタントの㈱アライブビジネスの淡河社長http://alive-business.com/
には、8月25日から公募が始まった、「平成23年度 省エネルギー革新技術開発事業(第2次公募)」の事例を取り上げ、助成金活用の着眼点について、記事を投稿していただきました。評判が良かったので、今後も投稿をお願いいたしました。さて、サポインについて、「部材の結合」分野の応募状況について、お問い合わせもいただきましたので、少し説明させていただきます。
この事業は、H18年度から始まった施策で、日本の製造業の国際競争力の強化と新たな事業の創出を目指し、それらを支える中小企業の「ものづくり基盤技術の高度化」に貢献する、革新的、かつハイリスクな研究開発を支援するものです。研究開発期間は2年度もしくは3年度、研究開発規模は初年度4,500万円以下(正確には募集要項でご確認ください)と大きく、ものづくり関連の支援事業予算の中でも大きなウェートを占めています。対象となる20の技術分野の中に、「部材の結合」すなわち「ねじ」も入っていますので使わない手はありません。経産省のホームページから、H18年度からH23年度までの20分野別の申請・採択状況の推移を以下にまとめてみました。ねじの分野の採択率はともかく、申請件数そのものが少ない残念な結果になっています。
何故、少ないのか?様々な理由があると思いますが、そのような支援事業があることの周知が足りないのであれば、未来開発パブリシティ委員会としても対策が必要になると思います。この制度は、ものづくりの川下、つまり、ねじのお客様のニーズに応えて行く技術開発を支援するものとも言えます。是非、ねじの未来をかけたチャレンジとして、次の公募に備えて、再度点検してみてはいかがでしょうか?
皆様の会社では、検討をされたことがありますか?
使わなかった理由には、どんなことがありますか?
ご意見などお寄せいただけるとありがたいです。 - メルマガ【ねじ未来開発・パブリシティ委員会ニュース】
-
(社)日本ねじ工業協会の未来開発・パブリシティ委員会(田島祥一委員長)は、パブリシティ強化の一環として、協会会員企業および関係先(ねじを取り巻く業際企業)幹部を配信先と想定した、ITを活用した記事配信を開始する予定です。
それに先立ち、2011年9月より、メルマガ【ねじ未来開発・パブリシティニュース】をトライアル配信を開始します。
トライアルの配信先は、以下の通りです。
・「未来開発・パブリシティ委員会」委員
・2010年10月に実施した協会50周年記念行事「ねじフォーラム」の参加者(メールアドレスを登録された方) - 未来開発・パブリシティ委員会が活動開始!
-
今年度から、日本ねじ工業協会に「未来開発・パブリシティ委員会」(田島祥一委員長)が発足し、既に活動を開始しています。
その目的は、
・ねじ産業の社会的な認知度の向上、ねじ産業従事者のモチベーション向上などを目的とし、内部向け・外部向けパブリシティ活動を強化すること。
・内部の連携を強め、外部特に「業際ネットワーク」の構築を推進すること。
・ねじ産業に関わる声を広く集め、ねじ産業の未来開発に関わる課題を共有して行くこと。
最初の取り組みとして、
・内部向けパブリシティとして、どんなテーマを扱うか?
・外部向けにどのような発信を行ってゆくか?
・パブリシティ活動を効果的に進めるために、どのようにITを活用してゆくか?
と言った課題について議論を重ねています。
以下は、今年7月、3回目の名古屋で行われた委員会の様子です。


このような委員会が生まれた背景について、少し触れておきたいと思います。
・これまで、協会の「ねじ産業未来開発プロジェクト推進委員会」から、様々なプロジェクト課題への取り組みが生まれました。それらの活動は各委員会ベースの活動として着実に動き出しています。
・また昨年は、50周年記念行事「ねじフォーラム」を実施した結果、ねじ産業に従事する方々をネットワークし、様々なねじに関わる課題を共有することの重要性を再認識いたしました。更に商社様、材料や設備会社様、あるいはユーザー様など、ねじの「業際」への発信や交流を強めて行くことによって、直面する様々な問題の新たな解決の糸口が見えてくるのではないかとの認識を持つこともできました。
・このような背景を踏まえ、各委員会のプロジェクト推進体制を整備するとともに、「ねじ産業未来開発プロジェクト推進委員会」は、「未来開発・パブリシティ委員会」として名前を改め、広報活動の充実発展という新たな役割を担うこととなりました。
現在までの未来開発・パブリシティ委員会において、委員から出た意見・要望を集約しますと、
まず、協会内部向けの広報として扱いたいという希望の多いテーマは以下の通りです。
①海外進出企業・海外競合企業の動向の紹介記事
②同業他社訪問インタビュー記事
③ユーザーニーズの収集・商社との連携
④中小企業施策・補助金の活用
⑤従業員の関心事、従業員教育
⑥ねじ業界内の情報公開
⑦ねじコミュニティ・本音議論の場が欲しい
⑧FacebookなどITの活用トライアルしたい
対外発信のテーマとしては、
①ホームページの改善、レベルアップ
②海外向け広報の強化
③規格の普及、ねじの安全設計の啓蒙促進
などが検討されています。
今後一つづつ優先度を決めて、条件の整った課題から、具体的な取り組みが始まると期待されています。続きはまた。
- 台灣區螺絲工業同業公會を表敬訪問
-
田島祥一副会長は、6月3日に、台灣區螺絲工業同業公會に表敬訪問し、蔡圖晉副理事長と面談し、同同業公會の会員企業から義捐金を寄せられたことに、感謝の気持ちを伝え、竹中弘忠会長からの感謝の手紙を直接手渡した。
- 台灣區螺絲工業同業公會からの義掲金を寄贈
-
竹中弘忠会長は、台灣區螺絲工業同業公會会員企業より東日本大震災の被災者に対して厚意で寄せられた、義捐金を特に被害の大きかった岩手、宮城及び福島の3県に寄贈するため3県庁を訪問した。
同会長は大磯義和専務理事と共に、6月29日午前に岩手県・保健福祉部の小田島智弥部長、同日午後に宮城県・保健福祉部の佐々木清司次長、翌日30日午前に福島県・保健福祉部五十嵐宏治参事(兼)社会福祉課長を訪ね、同同業公會より預かった義捐金をそれぞれ1,300万円寄贈した。
3県への寄贈にあたって、当協会と同同業公會のこれまでの友好関係並びに今回の義捐金を託された経緯について、竹中弘忠会長から「両会は、1年に1回交流の機会を設けており密接な関係を築いている。この義捐金は、陳明昭理事長から東京において直接手渡され当協会を窓口にと託されたものである。(社)日本ねじ工業協会会長として自らお渡ししたい。」と説明を行った。
宮城県庁において

- 台灣區螺絲工業同業公會からの義捐金について
-
○ 台灣區螺絲工業同業公會(理事長陳明昭氏)では、東日本大震災の被災者への義捐金を同同業公會会員から募った。
そして、当協会4月理事会開催に先立ち、その集まった義捐金4,600万円の目録が、陳明昭理事長から「被害総額は10兆円を超えると聞いており、微々たる金額ですが、少しでもお役に立てればと思っている。」とのコメントを添えて、竹中弘忠会長へ直接手渡された。
それに対して、同会長より、「陳明昭理事長及び台灣區螺絲工業同業公會会員の皆様に心より感謝申し上げますとともに有意義に使わせていただきます。」とのお礼の挨拶があった。
○ 同理事会終了後、寄贈された義捐金の受贈先、受贈方法等について意見交換を行なった。
それを受け同会長より、理事会におけるご意見を参考に政策委員会・幹部会で義捐金の受贈先、配分方法等について検討を行なう旨の説明があった。 - 会合委員会、部会等開催状況 (2011年3月末から7月まで)
-
○ 資格委員会(技術委員会資格制度WG)準備会
日時:①4月13日(水)11:00~
②5月17日(火)11:00~
場所:機械振興会館
議題:平成23年度の運営について○ 建築用ねじ部会
日程:3月28日(火)15:00~17:00
場所:関西支部会議室
議題:○タッピングねじ等に係る建築工事管理指針について
○部会運営について
参加者:12名○ ねじ産業未来開発プロジェクト推進委員会(未来開発・パブリシティ委員会)
日程:4月21日(木)16:00~
場所:ホテル日航大阪
議題:平成お年度委員会事業について○ 役員選考委員会
日程:4月21日(木)13:30~14:00
場所:ホテル日航大阪
議題:全支部役員候補報告及び承認 - 4月理事会
-
1.日時 平成23年4月21日(木)14:00~15:20
2.場所 大阪ホテル日航大阪「白鳥の間」
3.出席者数 57名(本人出席32名、代理出席3名、書面をもって議決権を行使する理事22名)
4.議事
冒頭、理事会に先立ち、台灣區螺絲工業同業公會理事長陳明昭氏より、東日本大震災の被災者への同同業公會からの義捐金4,600万円の目録が、竹中会長へ手渡された。(以下、「台灣區螺絲工業同業公會からの義捐金について」参照)
大磯専務理事より本日の理事の出席状況について、本人出席32名、代理出席者3名、書面をもって議決権を行使する理事22名、計57名(欠員2名)で本理事会が有効に成立している旨の報告があった。
竹中会長の開会挨拶の後、経済産業省製造産業局産業機械課係長伊藤昌洋氏より、東日本大震災復興支援に関する施策(補正予算関連(案)等の紹介を兼ね挨拶があった。
竹中会長が議長となり、議事録署名人として議長のほか長谷川副会長、嶋田副会長の2名を選任して議事に入った。議題1総会付議案件について
(1)平成22年度事業報告書(案)並びに平成22年度決算報告書(案)
大磯専務理事より、資料「平成22年度事業報告書(案)及び資料「平成22年度決算報告書(案)」に基づき、委員会・部会の事業実施状況、会費収入状況及び収支状況について説明すると共に、引当資産として事業遂行引当資産を積立てた旨の説明があった。
議長より、両案を議場に諮った結果、原案どおり承認された。(2)平成23年度事業計画書(案)及び平成23年度収支予算(案)
大磯専務理事より、資料「平成23年度事業計画書(案)及び資料「平成23年度収支予算(案)に基づき、各委員会・部会等事業計画(案)を説明すると共に、会員の退会に伴う会費収入
減を見込んだ収支予算(案)となった旨の説明があった。
また、事業計画(案)については各担当委員長より詳細の説明があった。
議長より、両案を議場に諮った結果、原案どおり承認された。(3)次期役員候補等(案)
長谷川副会長(全支部役員選考委員長)より、総会に付議する次期役員候補者については、選考委員方式で選考すること及び各支部の役員選考委員会において次期役員候補者を選定して、本理事会前に開催した「全支部役員選考委員会」で支部毎の役員候補者案を審議検討。そしてその結果、「次期役員候補等(案)」を決定した旨の説明・報告があった。
議長より本案を議場に諮った結果、原案どおり異議なく承認された。(4)平成23年度会費規程(案)
嶋田副会長・財務委員長より、資料「平成23年度会費規程(案)」について、現行の会費規程を継続いたしたい旨の説明があった。
なお、新会費規定は、実情に即した見直したい旨の補足説明があった。
議長より、平成23年度は現行会費規程を継続することについて、議場に諮った結果、異議なく承認された。
なお、議長より議題1総会付議案件((1)~(4)の各議案)は本日全て承認を頂いたので、来る5月26日(木)開催予定の通常総会に付議し、承認を頂くこととしたい旨の説明があった。○報告事項
大磯専務理事より、報告事項について、前回報告以降の会議等開催状況、今後の会議等開催予定について説明・報告があった。
以上で議事の全てを終了し、15:20閉会した。


-thumbnail2.jpg)
-thumbnail2.jpg)
-thumbnail2.jpg)