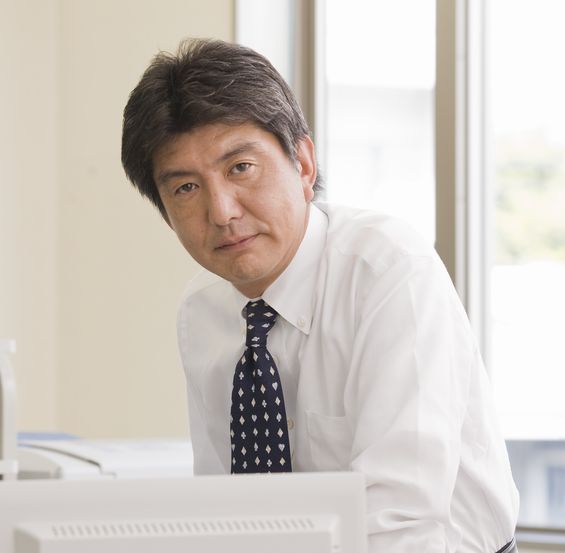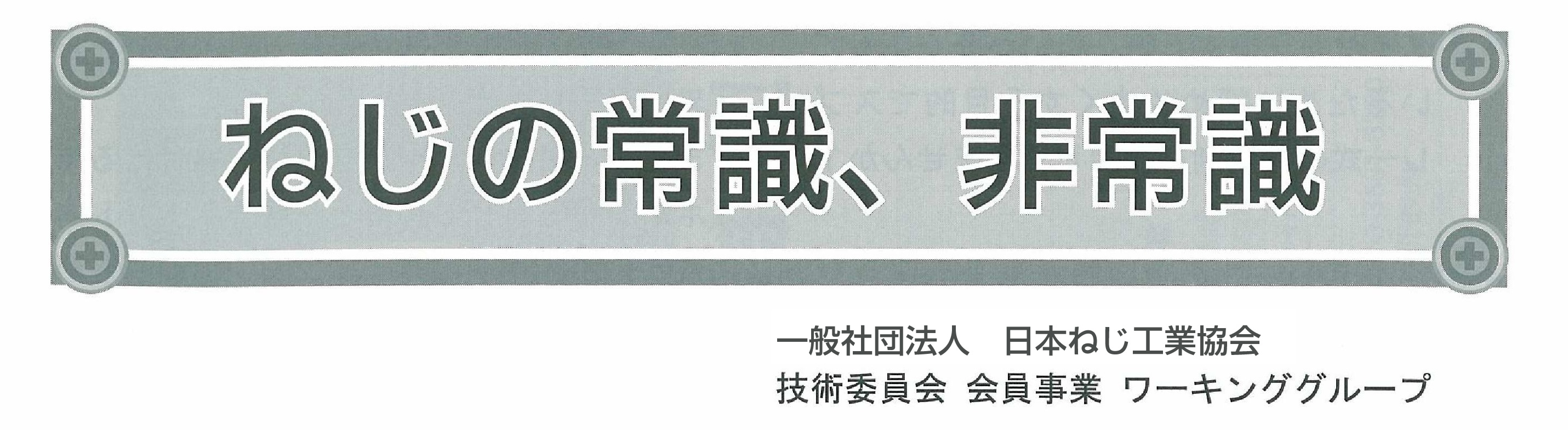会報ねじ 新着記事
- クラウン精密工業株式会社 代表取締役社長 望月紀人氏
-
「トップに聞く」
クラウン精密工業株式会社
代表取締役社長 望月紀人氏
聞き手 未来開発・パブリシティ委員会「トップに聞く」グループ
インタビューサマリー
・ 会社概要
望月紀人 (もちづき すみと)
1962年生まれ。1984年、立教大学 経済学部を卒業。3年間の修行を経て、1987年、クラウン精密工業株式会社に入社。2003年、専務に就任。2007年、代表取締役社長に就任。
海外も同時に特許申請 戻る
―― タッピンねじにはどのような市場があるのでしょうか。
望月 通常は「めねじ」に「おねじ」を入れていきますが、「タッピンねじ」には「めねじ」がなく、穴だけ開いていて「おねじ」を締めることによって「おねじ」自身が「めねじ」を切っていきます。その市場は、特定の業界、分野ということではなく、ねじをある程度たくさん必要とするところでは、結構使われているのが実態だと思います。家電やOA機器、車関係でもテールランプとかミラー系とかにはよく使われます。
「めねじ」が必要ないので、工程が一つ減る、言い換えればコストダウンということになると思います。
―― 御社のオリジナル商品について紹介していただけますか。
望月 「デルタイト」は、いわゆるタッピンねじで、一番販売力の高いものです。特徴は、締め付けトルクが非常に低く、破壊トルクが高いことです。そのためお客様が工場で使用する際に、締め付けをするトルクの自由度が高くなっています。
「ブラックス」は、鉄板ではなくて合成樹脂用のタッピンねじです。
「ショルデック」は、座付ねじにスペーサーを組み合わせて、不完全ねじ部ゼロの段付きねじです。以前はモーターによく使われていました。今は、照明などの狭いスペースに使われています。
「ビューヘッド」は、スペースの制約や美しさを重視するときに使用する 頭の薄いねじです。頭を薄くすると、十字穴が軸まで届きやすくなり、頭飛びの危険性が高くなりますので、首下に少しアールを付けて広くするなどの工夫をしています。
さまざまなオリジナル商品
「ボリウェーブ」は、座金の部分が三角に折ってあって、締めるとそれが相手に食い込んで、ばねの代わりをするので、緩み難いねじです。
「ボリデルタイト」は、ポリウェーブの足をデルタイトにしたものです。
「リップネジ」は、薄い板用のタッピンねじです。ねじの山と山で相手の板を挟み込むようなイメージで締め付けます。普通のねじ山は60度ですが、このねじは45度になっています。
「リブロック」は、溶接ボルトの代わりになるもので、頭の下に突起を出しておいて、押し込んでかしめることで締結するねじです。
「スリードライブ」は、頭を大きくして、手で回せるようにしたものです。結構需要があったので、それを企画化して作りました。
―― どのようなきっかけで、オリジナル商品の開発に至るのでしょう。
望月 お客様の困りごとがきっかけとなることが多いです。薄頭のビューヘッドも、「頭が邪魔なんだけど」というお客様からの要求から開発したものです。やはり創業当初から開発商品を出してきていましたので、そういう姿勢が根付いているのかもしれません。
あとは特徴的なのが、一つひとつにデザイン的なパッケージを作って、出荷する箱にもそのデザインを施していることです。一つひとつの商品を育てていきたい、知名度を上げていきたいという思いは強いです。
―― オリジナル商品では特許を取得していますが、ご苦労もあるのではないかと思います。
望月 やはり手間はかかりますね。海外で形状や工具を真似される可能性も考慮して、最近では海外の特許も同時に申請しています。特許は、日本で取得した後に、海外に申請することができませんから。
―― タッピンねじはどれくらいの割合ですか?
望月 8割程度だと思います。ボルトも多いのですが、お客様の図面仕様でねじ部がデルタイトということもあるので、正確なデータを取るのは難しいですね。
―― 熱処理も御社でやっておられますね。
望月 熱処理は、比較的最初のころから設備しましたが、なかなかうまくいかなくて、当初は随分苦労したようです。
基本的にタッピンねじはじぶんで「めねじ」を切っていくので、表面が硬くなくてはならない。でも全部硬いとパリッと割れてしまいますから、「湿気たおせんべい」のように、中は柔らかくて外は硬くなければいけません。最近は相手の板が硬くなっているので、この熱処理が結構難しいんです。しかも、お客様は意外と勝手に板を変える。ある日突然ねじが入らないということがあります。当社の場合は、社内で熱処理設備を保有しているので、熱処理条件を変えて、より表面を硬く、中は柔らかくする条件を探していきます。
熱処理を社内でするかどうかは、コストとの兼ね合いになるとは思いますが、作ることへのこだわりですね。そういうこだわりって、必要なのではないかと思います。
状況が変化しても、核となる理念は継承したい 戻る
―― 御社はどのような経緯で創業されたのでしょうか。
望月 私の父の兄が、「クラウンラジオ」という会社で、ラジオとかテレビを作っていました。私が幼いころ、家の家電製品は全部クラウンだったことを覚えています。
今回インタビューがあるので調べてみましたら、戦後の日本の輸出産業は、トランジスタラジオが中心で、大手が参入する前は、ほとんど中小だったようです。叔父の会社も基本的には輸出メーカーだったので、あまり日本での販売はしていませんでした。1955年ごろは銀座4丁目の鳩居堂の上に看板を出していたようです。当時はかなり勢いがあったのですね。
ラジオを作るにはねじをたくさん使うし、ねじは機械が作るので人が少なくてすむこともあって、ねじを作ったらいいのではないかと、クラウン精密工業が生まれたと聞いています。昭和35(1960)年10月に設立、昭和36(1961)年6月に、朝霞のクラウンラジオの一部に工場を建設して生産を始めました。その後、業務拡大に伴って、現在の本社がある志木に工場を建設し、移転したのが昭和36(1961)年です。 同年の9月に日立営業所、翌年の11月に名古屋営業所を開設しました。
本社工場外観(埼玉県志木市)
―― 子会社の展開もしておられますが、それぞれどのような役割なのでしょうか。
望月 基本的には、生産品目が異なります。ヘッダーの素材であるワイヤは、私どもでは1ミリ~12ミリぐらい使用しますが、その線形で分けています。それぞれ特化することで経営を効率化できることが一つと、それぞれの法人で利益を出すことによる経営責任の確立、人材育成を目的としています。
山梨県のクラウンファスナーは、現在、私の弟が社長を務めています。
クラウン精密秋田工場は青森に近い場所です。今は北秋田空港ができましたが、以前は秋田から3時間ぐらいかかりました。高度経済成長のころはなかなか人が集まらなかったので、なんとか人を集めたいと、東北の方を探していて紹介されたと聞いています。
福島のシーエージーは、ヘッダーの多段機の専門工場です。多段機ではお客様の図面をいただいて、特注品を作るので優位ですが、機械を多くは所有していなかったので専門工場を建てたようです。
秋田のクラウンメタルプレイティングは、メッキ処理の工場です。青森に近いところにある工業団地で、熱心な誘致を受けました。熱処理と同様に、表面処理も外注さんにお願いすることが多いのではないかと思いますが、たまたま中国工場でメッキを内製化したので、日本でも競争力をつけるためにメッキ部門があってもいいのではないかと。メッキは排水の問題などがあって、認可をいただくまでに交渉が必要でした。秋田では、圧造、転造、熱処理、メッキが、一貫生産できる体制になっています。
―― 香港、中国、タイと、海外にも進出しておられます。
望月 香港が平成6(1994)年、中国が平成7(1995)年です。当時はお客様の中国進出が激しく始まっていた時期でした。
タイ工場は、平成13(1991)年設立で、平成17(2005)年にロジャナ工業団地に移転しました。ロジャナ工業団地は、2011年のタイ洪水の被害に遭ったところです。完全に水没して水が引くまで1か月くらいかかりました。それから機械の修理をしましたが、全部ドロが入ってしまって、中には日本に持ってきて修理をしたものもありました。結果的に、2年ほど遊ばせる形になりました。
―― 「創造性豊かな高付加価値商品を生み出すことによって広く社会に貢献し、社員の幸せと夢のある企業を目指す。」という経営理念について、どのように考えておられますか。
望月 昭和60年に理念が作られたときは、まだ私は入社していませんでした。創立から25年ぐらいたったころで、おそらく会長の中で理念が必要だと考えたのだろうと思います。社員綱領も同時期に作っています。
本社事務所に掲げられた社是(中央)経営理念(右)社員綱領(左)
私としては、これを継承していきたいという気持ちを強く持っています。周りの状況は変わっても、中心にある考え方は、経営するうえでは継承していきたい。できてから20年ぐらいたっていますが、変えようとは思っていません。
社員は、経営理念、社是、社員綱領と、会長が好きな言葉が書いてあるカードを持っています。迷ったときはこれを見るようにということです。
受注から出荷までの一元システムが効率化に貢献 戻る
――平成4(1992)年というかなり早い時期に、コンピューターシステムを導入しておられますが、どのような経緯で導入したのでしょうか。
望月 それまではそれぞれの場面では管理していても、今どの工程に行っているかは、ずっと品物を追いかけて探さなければならず、それを何とかしたいと思いました。それまでもコンピュータがなかったわけではないのですが、部署ごとの電算システムでした。それを受注から出荷まで、グループ工場を含めて一元管理をするようにしました。かなり効率が上がったと思います。
――大がかりなシステムの導入にあたっては、いろいろなご苦労があったのではないかと思います。
望月 当時はオフコンで、こちらに知識がないので、SEと話をしても会話にならない。出力帳票も一つずつイメージを書いてもらったりしました。SEは各部署のヒアリングをして、それをつなぎ合わせて...... かなり大変な作業でしたね。投資額も億単位です。
また当時は、キーボードすら打ったことがない人もいっぱいいて、それまでは台帳管理でしたから抵抗感もかなりありました。ある時期までは、台帳と新しいシステムを並行して走らせましたが、なかなかシステムに入力してくれないということもあって、立ち上げ時は相当苦労しました。
バージョンアップもかなりしています。現在は、どの品物はどこまで進んでいるか、画面ひとつで追いかけられるので、もうこのシステムがなかったら仕事ができない状態ですね。
――ISO9001、ISO14001、QS9000にも取り組んでおられますが、大変ではありませんか?
望月 私はあまり大変だと思っていなません。ISOの環境も品質も、自分たちがやっている業務を、ISOの要求のどこに当てはまるか考えて、落とし込んでいる感じなので、そのために余計な仕事が増えたという感じはしていませんね。
たとえば、ISOでいう「マネージメントレビュー」も、私どもでやっている月1回のリーダー会議に置き換えて、議事録のフォーマットもISOの要求に合わせています。QS9000の「製品品質日程計画」には、我々なら工程管理表を当てはめようというように。システム導入前から、工程管理表は作っていましたし、社員の抵抗もあまりありませんでした。
人事評価は、透明で分りやすく 戻る
――人事評価はどのようにしていらっしゃいますか?
望月 5年前から制度を変えました。17のランクに分割した給与体系になっていて、社員は期首に設定される会社の目標や、その課が掲げる目標に対して、個人目標を設定します。その目標にそって、達成度、貢献度、成果を自己申告し、上長とすりあわせて、社員のやる気や自分の成長の度合いを自己評価、客観評価で見るという方法です。
成果主義といっても既得権がありますから、大きく従業員の不利益にならないように、かなり慎重に作りました。
――なぜそのような制度に変えようと思ったのですか?
望月 人事評価では毎年悩むので、もう少し客観的な評価はできないかと。たとえば製造現場なら、担当する機械によって仕事量が変わることもあるし、営業だって自分でお客様を選べるわけではない。ある程度透明性があって、従業員の皆さんにも分りやすいことが必要なのではないかと思いました。
――運用していくうえで、難しいことはありますか?
望月 人によって、自己評価が辛めの人、甘めの人がいます。そこはコミュニケーションを重ねながらやっていくしかない部分ですね。本当は、評価をする管理者のトレーニングもしなければいけないのだと思います。経営側から見えている管理者と、部下から見えている管理者の評価は、意外とずれていたりしますので、気を付けなければいけないと思っています。
――社員による自主的な改善活動などは行われていますか?
望月 「活動」と呼んではいませんが、毎期、社長指針を出しているので、それに基づいて各課が1年間の活動計画を立てています。たとえば、現場のヘッダーであれば、工具の再生化とか、スクラップ量の低減といった目標を決めて、その進捗管理をしています。
以前は、具体的な内容の社長指針を出していたのですが、指針が具体的だと、社員の自主性やアイディアが広がらないので、今は抽象的な指針を出すようにしています。
「販売無くして生産なし、販売無くして経営なし」 戻る
――ねじの市場の変化をどのように見ておられますか?
望月 3~4ミリはボリュームゾーンだとは思いますが、私どもでは意外と5ミリ以上も多いです。それは、逆に3ミリ以下の仕事は、日本からどんどん無くなって、海外にいっているということだと思います。
たとえば、テレビはまさに3~4ミリの仕事で、私どもがテレビのねじを作っていたころは、1か月の売り上げがテレビだけで2000万円ありました。それが今はゼロです。昔はカセットテープとかビデオテープとか、デッキの中にいろんなものがついていましたから、ビデオ関係の仕事も多かったのですが、今はほぼゼロですね。コピー機も、昔は1台で600本ぐらいねじを使っていましたが、今は200ぐらいだと思います。ねじ締めは、作る方には余計な工数なので、なるべくねじを減らしたいと考えるのは当然ですからね。
市場はめまぐるしく変化していますから、「今のものはいずれ消滅していくんだ」というくらいに考えて、常に新しいものを追いかけていかなければなりません。
――そのような市場において、どのような事業戦略を取っていかれるのでしょうか。
望月 基本的には、私は「販売無くして生産なし、販売無くして経営なし」と思っています。とにかく受注を確保していくことが大前提だと思っています。
我々の場合、意図的ではなのですが、10%を超えるお客様はなく、どこか1社に大きく依存していることがありません。リスク分散という意味では強いのですが、常に新しいものを取り続けないと同じ売り上げを維持することができません。われわれが保有している設備の範囲内で、それが製造できるのであれば、どんなものでもトライしていきますし、情報を収集するなかで必要と判断した設備には、積極的に投資をしていくという考えです。
もう一つは横展開です。2か月に1回、会議を開いて、今新規でどういうお客様に行っているか、我々の実績ある商品をどこに売り込んでいるのかを情報共有しています。
ISOの認証も、検査設備も、品質の要素ですが、一番大切なことはそれがどういうところに使われるかだと思います。私どもでは、まず用途を確認します。そうすると目的に応じて、そこまで厳しくなくてもいいのではないかなど、こちらから提案ができる。次にそれを工具の設計に落とし込んで工具図面を描く。基本的にはヘッダーも工具で作るのですから、工具の品質の一定化は大切な要素ですし、難易度の高いものは工具も内製して、ノウハウを蓄積しています。規格品よりもお客様の図面で作るものが多いので、こういう動きをすることで、我々の付加価値を提供できると思っています。
――設備投資の具体的な計画はありますか?
望月 今のところ国内では考えていません。海外に関しては、今ある中国、タイの工場の機械設備を良くして、今海外でできていない仕事を取って、生産品目を変えていくということを考えています。
――ねじ以外に進出する可能性は?
望月 今でも当社は切削もしています。ねじとあまりかけ離れた分野は考えていませんが、いわゆる機械加工であれば、十分ありうると思います。
会社を永遠に存続していきたい 戻る
――昭和62年に入社されましたが、入社前は何をしてこられましたか?
望月 昭和59年に立教大学の経済学部を卒業しました。その後、大陽ステンレススプリングさんで、工場で1年、営業で2年修業をさせていただいてから、クラウン精密工業に入社しました。
――お父様からは後を継ぐように言われていたのでしょうか。
望月 父からは入社しろとは言われていませんでした。自分では入るものなんじゃないかと思っていましたので、大学卒業が間近になって就職ということと向き合った時に、初めて父にクラウン精密工業に入ってもいいと話しました。子供のころから父とはあまり接点がなかったですし、入社してからは社長と一般社員ですから、ずっと敬語で話していました。妻は変な親子だと思っていたようですね。
――社長に就任されるまで、どのような仕事をしてこられましたか?
望月 当社に入ってまず感じたのは、お客様と接する時間よりも、社内の調整をしている時間が長いということでした。注文が入ると、自分で工場に行って要請する。急ぎの案件も、誰か一人に伝えればよいのではなくて、圧造に行ったり、転造に行ったり、あちこちに頼んでやっと出来上がる。それを今度は自分で倉庫から引っ張り出して、自分で納品書を書いて、お客様に届ける。そういう状態を見ていて、営業なら純粋にお客様と折衝する時間とか、あるいは技術的な勉強をして「ねじ屋」的な営業をしていかなきゃいけないと思いました。そこで営業の中の業務を受け持つ部署を作ったり、配送部門を作ったり、コンピューターシステムを導入したり......。私から見て会社の弱い部分を強化していくということを、自分なりにやってきたと思います。
修行先では、納品というとライトバンに積んでいきましたが、当社に入社した当時、車は全部トラックでしたからね。自分で2トントラックを運転して納品に行くというのは、カルチャーショックでしたね。
――記憶に残る出来事はありますか?
望月 営業をやっていたとき、あるお客様から「たぶんクラウンさんとの取引は、今が一番いい状態だよ」と言われたことがあります。その理由は、「あんたが社長の息子だから」。たぶん社内的な影響力もあるし、私が言えば早く上がってくるのではないかと。その時に、何をやってもそういう風に思われるのかなと思いましたね。できて当たり前、人の倍やって当たり前みたいなところはあるのかなと。
自分ではあまり意識していませんが、負けたくないという気持ちはありました。私が入社したことで、前任者はお客様を取られているわけですよね。理不尽な話ですよね。その限りは、信頼を得なければいけないなという気持ちは強かったですね。
ですから香港にも最初に行きました。自分が行かなかったら次の人を行かせられないと思いましたので、売り先を探しにまず自分が行きました。時には、自分がやったことがなくても誰かにやらせることは必要でしょうけれど、心苦しいという感じはしますね。
――社長として、将来に対してどういう思いがありますか?
望月 一番の思いは、会社の永遠の存続ですね。これだけ周りの環境が変わっているので、会社の中身も変わっていかざるを得ない、変えていかなければいけないかもしれない。そういう意味では、当社の場合は、お客様の声を聞く、自分たちで自分の事業領域を決めないということをモットーに、形を変えながら永遠に会社を存続していきたいという思いです。
自分の父親を亡くしたときに、人って、そこですべて終わってしまうんだなと思いました。どんなに情熱を傾けて、どんなに思っても、人って終わるんだなと。それで、この会社を次世代に繋いでいきたいという思いが強くなりましたね。
――最後に、業界、あるいは協会に対する思いをお聞かせください。
望月 ねじ屋さんでは、戦後すぐに取引が始まって、伝統的にどこかの売上比率が40%も50%もあるとか、昔からの付き合いで間違いなく仕事が来るという会社が意外と多いと思います。我々はまったく逆で、最初にねじの会社を作って、それから売り先を探してきた会社なので、そういう状況に一度たりともなったことがありません。結局は一社一社の自助努力しかないのではないかと思います。
協会といえども、それは各社のまとまりなのですから如何ともしがたい部分はあると思いますが、自分たちがそこに参加する思いは違っていいと思います。こういう仲間や業界に携わっている人たちがいて、情報交換の場であったり、思いを共有できる場であったり、自己研さんの場にもなる。そういう場でいいのではないかと思います。
―― 貴重なお話をありがとうございました。
クラウン精密工業株式会社 ホームページ: http://www.crown-screw.co.jp/
――――――――――
【会社概要】 戻る
設立 昭和35年(1960年)10月15日
代表者 代表取締役社長 望月 紀人
資本金 12,000万円
従業員数 国内:250人(グループ企業含む) 海外:400人
事業内容 冷間圧造によるねじ及び締結部品の設計、製造、販売
製造品目 デルタイト ® (ねじ込みトルクの低いねじ)
ポリデルタイト ® (ゆるまないトルクの低いねじ)
ポリウェーブ ® (ゆるみ止ねじ)
プラックス ® (合成樹脂用ねじ)
リップねじ ® (薄板用ねじ)
リブロック ® (スタッドボルト)
ショルデック ® (不完全ねじ部ゼロの段付ねじ)
ビューヘッド ® (外装用ねじ)
ノジロック ® (ゆるみにくいねじ)
マイクロファスナー (極小圧造部品・ねじ)
特殊圧造部品
小ねじ
タッピンねじ
所在地・拠点
本社
〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡4-7-31
秋田工場(㈱クラウン精密秋田工場)
〒018-3333 秋田県北秋田市坊沢字深関沢13-2
福島工場(シーエージー㈱)
〒963-7827 福島県石川郡石川町新屋敷字長土路48-2
山梨工場(クラウンファスナー㈱)
〒400-0402 山梨県南アルプス市田島818
クラウンメタルプレイティング㈱
〒018-3300 秋田県北秋田市市川井字横呑沢5-133
日立営業所
〒317-0000 茨城県日立市東多賀町3-6-12
名古屋営業所
〒485-0000 愛知県小牧市久保本町103
東莞皇冠螺絲有限公司(中国)
広東省東莞市長安鎮涌頭管理区
ECF PRECISION CO.,LTD.(タイ)
55 Moo 5Rojana Industrial Park
Tambol Utai Amphur Utai Ayutthaya 13210
日皇精工有限公司(香港)
Unit T, 4/F., Valiant Industrial Center, 2-12 Au Pui Wan St.,
Fo Tan , Shatin, N.T. HongKong
経営理念
創造性豊かな高付加価値商品を生み出すことによって広く社会に貢献し、
社員の幸せと夢のある企業を目指す。
社是 誠実・不屈の精神・創意工夫
社員綱領
1.良い品を安く、早く、造り顧客の信頼を得ること。
2.研鑚に努め、人格と能力の向上を計ること。
3.清潔で整頓された活力ある職場をつくること。
4.社会人としての自覚を持って社会との調和と共栄に努めること。
――――――――――
記事:ワッツコンサルティング㈱ 杉本恭子
- 大矢螺子工業株式会社
-
昨年当協会に正会員として入会された、大矢螺子工業株式会社様に、「私の会社紹介」への投稿記事を作成して頂きました。
【特殊な形状のねじにも対応。高品質・高精度で、顧客満足を追及 】
<プロフィール>
 会社名
会社名 大矢螺子工業株式会社
代表者
大矢 正継(まさつぐ)
所在地
愛知県名古屋市中村区太閤5-20-10
~創業以来、高品質な製品を安定供給~
大矢螺子工業株式会社は、高品質な産業用ねじを安定供給し続けている総合ねじメーカーです。創業は戦後間もない1947年。2003年には品質マネジメントシステム「ISO9001:2000」を取得しました。2009年には60周年を機に着手した新工場をオープン。
最新設備を備えた新工場では塑性加工技術をフルに発揮し、製品の生産性および
品質状況をより高めております。製品種目としましては、多彩な螺子類をはじめ、自動車部品、弱電部品などです。
中でも主力は精密ねじ付部品で、様々な加工データの蓄積を金型製作や製品設計に
反映することで特殊な形状のねじ生産も可能にしています。また高品質、そして少量多品種生産、短納期、こうしたご要望に添う対応力を
備えています。熱処理や表面処理、切削加工などの協力会社とも連携し、確実に
作り込みができる体制を整えているのも強みです。
~理念は、顧客満足を追求し、信頼される製品を提供すること ~
 創業以来、当社が大切に貫いている経営理念は、
創業以来、当社が大切に貫いている経営理念は、
顧客満足の追求です。お客様のご意見に耳を傾け、ご要望をしっかりと汲み取り、精度の高いねじを作りご満足いただく。お客様とともにものづくりを進め、信頼関係を築くことを何より重視しています。おかげさまで品質・性能をご評価いただき、愛知県はもとより、東京、大阪など日本各地の自動車部品関連会社様と取引をいただいております。
~若い力を活用し、新しいフィールドへもチャレンジ ~
経済・産業のグローバル化に伴い、多くの自動車メーカー様が海外に進出している今、
当社も広い視野で事業展開していくことを念頭に入れています。価格競争や為替リスクなど
課題はありますが、これまで培った技術と経験を生かし、市場の拡大や創出に努めて
いきたいと考えます。その原動力となるのが、若い力です。当社では若手の社員が数多く在籍し、時代に
呼応したものづくりに取り組んでいます。今後は、世界を見据え果敢にチャレンジする
人材を育成し、新しいステージへ。さらなる成長を目指してまいります。 - 平成25年「ねじの日」を迎えて
-
昭和50年7月15日にねじ商工連盟(一般社団法人日本ねじ工業協会と日本ねじ商業協同組合連合会で構成)総会で「ねじの日」(6月1日)が制定されて、早いもので38年目を迎えます。ご高尚のとおり、昭和24年6月1日に新しくJIS制度が制定され、それにちなんでこの日を「ねじの日」と定められました。ねじの製造、販売に携わる者の社会的責任等についての認識を深め、かつ社会一般にねじの基礎部品としての重要性を周知することを目的として「ねじの日」が定められました。昔から「ねじ」は産業の塩と呼ばれ、「もの」と「もの」を締結する部品であり「ものづくり」にとってなくてはならない重要な基幹部品であります。またその品質は機械工業、住宅、橋梁等の性能・安全を大きく左右するとの認識のもと、ねじメーカーは今日まで技術開発、商品開発に積極的に取り組み、高品質で優れたねじ類を日本並びに世界各国へ送り出してきました。「MADE IN JAPAN」は、日本並びに世界各国の機械工業等の発展に大きく寄与し、その品質・性能は内外のユーザーから高く評価されております。ねじは、また「もの」と「もの」を締結するだけでなく、自動車、家電製品、住宅等を通じて、人々の快適で安全な日々の生活を影で支えており、生産活動、人々の暮らしの隅々までかかわっております。経済のグローバル化に伴い、わが国ねじ企業はアジア企業等々と激しい価格競争・市場競争を強いられております。熾烈な国際競争に勝ち残り、わが国ねじ産業の地位を確固たるものにするためにも、世界の舞台で活躍できる人材の育成、新製品の開発、経営基盤の強化等が急務となっております。その対応策の一環として当協会では、次の事業を強力に推進しております。資格委員会が進めている、ねじ製造技能検定制度の確立です。この事業は、ねじ製造技術者・技能者の技術力並びにわが国ねじ産業の技術水準の向上を図ると共に、新商品の開発・生産に繋げる人材育成のための大事な事業です。平成23年度及び24年度にねじ製造技能検定2級試験(協会認定)を実施しました。技能検定試験(協会認定)を、あと数年実施してその成果を基にねじ製造技能検定国家認定資格制度の創設を厚生労働省へ申請することにしております。また、平成23年度に厚生労働省のご指導の下「ねじ製造業の職業能力評価基準」を作成しました。平成24年度にはこの職業能力評価基準に基づきキャリア形成過程をモデル化したキャリアマップ及び職業能力評価シートを作成しました。ねじ企業の人材育成並びに職業能力評価への活用をホームページ等を通じて広く働きかけるなど、世界に羽ばたける人材育成の支援態勢を推進しております。"ねじ"なくしては、生産活動、人々の暮らしに支障をきたすと思っております。「ねじの日」に心を新たにし、世界に冠たるねじの開発・生産に努め、工業立国日本を再生し、ねじを通して社会貢献並びにねじ産業の発展に尽くしてまいる所存です。どうか皆様のなお一層のご支援、ご協力を心からお願い申し上げる次第です。最後になりましたが、会員はじめねじ産業に関係する皆様方のご発展並びにご健勝を心よりご祈念申し上げて、「ねじの日」のご挨拶とさせていただきます。
- イズラシ、先進的な「認知動作型トレーニングマシン」を設置したスポーツジムをオープン
-
株式会社イズラシ様からの投稿がありました。事務局にて取材に基づく情報を加え、記事にしました。
イズラシ、先進的な「認知動作型トレーニングマシン」を設置したスポーツジムをオープン
~ 新たな事業の柱を目標に、トレーニングマシンの製作にも着手 ~
株式会社イズラシ(本社:静岡県沼津市大岡)は、2012年9月、沼津の新社屋の敷地内に「アイシック健身塾」をオープンしました。アイシック健身塾は他のスポーツジムにはない、「認知動作型トレーニングマシン(※1)」を使ったトレーニング施設で、マラソンや登山の体力作りに最適な国内最大級の低酸素トレーニングルームも完備しています。現在、小学2年生から80歳超える方まで、あらゆる世代の会員が在籍し、競技技術向上から健康維持までさまざまな目的でトレーニングをしています。
本社屋に併設されたアイシック 健身塾の外観
サインボード
「個人差はありますが老齢化に伴い、60歳を過ぎた頃から歩行時の歩幅が狭くなり、転倒やつまずきといった歩行障害などの発生リスクが非常に高くなってくると言われています。当塾では歩幅減少・歩行障害の予防および改善を目的とした、「スプリントトレーニングマシン」での運動を提供し、すり足動作による歩幅減少の改善、足の回転運動による大腰筋強化により歩行障害の発生リスク低減に努めています。」(アイシック健身塾 今井勇太氏)
様々な認知動作型トレーニングマシンが並ぶジムの様子
またイズラシは、新社屋のオープンを機に、新型トレーニングマシン開発事業として「ファルマバレー事業部」を創部し、「認知動作型トレーニングマシン」の製作に着手しました。
「新しい工場には社員のためのジムを作るつもりでしたし、健康産業にも以前から興味を持っていました。ある企業から、東京大学の小林寛道名誉教授がアスリートのために研究している「認知動作型トレーニングマシン」を紹介されたことがきっかけで、弊社でもトレーニングマシンの製作に着手することを決意しました。マシンの図面をいただき、コンパクトにするなどデザインを工夫し、現在までに8種類を製作しています。今後も順次機種を増やしていきたいと考えています。」(代表取締役 堤親朗氏)
認知動作型トレーニングは、静岡県のファルマバレープロジェクト(※2)第2次戦略計画に「科学的手法による健康づくり」として取り入れられた理論で、イズラシの参入はトレーニングマシンの製造拠点として期待されています。
イズラシでは、アイシック健身塾によって会員に価値あるサービスを継続的に提供し、健康への新たな可能性を追求したいと考えており、ファルマバレー事業部とも連携し、新型トレーニングマシンの研究・開発・実証を推進していくとしています。また、将来的にはトレーニングマシンの医療機器認定も検討し、今後は健康産業を同社の事業の柱の一つとして成長させたい考えです。
※1 認知動作型トレーニングマシン
体幹深部筋肉の強化(脊髄・骨盤・膝関節)と脳・神経と筋肉の連係動作を確立し、運動パフォーマンスを向上させ、身体能力を高める事ができるマシン。認知動作型トレーニングマシンを使用する事で、足が速くなった、姿勢が良くなった、肩こりや腰痛が軽減されたなどの実績が報告されている。最近の研究では、インナーマッスル(体幹深部にある筋肉)を使う運動が、脳を刺激し活性化させることが明らかになってきている。
※2 ファルマバレープロジェクト
静岡県が、県東部地域を中心に、地域の民産学官が協働して推進しているプロジェクト。平成8年、県立静岡がんセンターの基本計画策定時に「県立静岡がんセンターを核にした医療城下町を作ってはどうか」との意見に端を発して、平成13年、富士山麓先端医療産業集積構想(ファルマバレー構想)を策定した。
アイシック健身塾 : http://www.issic.co.jp/
- 嶋田 亘 副会長が旭日小綬章受章
-
平成25年春の叙勲で、当協会副会長、㈱フセラシ取締役会長 嶋田亘(しまだ わたる)氏は、当協会副会長として永年に亘り協会事業推進に献身し、もって 我が国ねじ業界の振興・発展に多大な貢献した功績により旭日小綬章を受章いたしました。勲章伝達式は5月14日、ザ・プリンスパークタワー東京「ボールルーム」において挙行され勲章等が伝達されました。伝達式の後、受章者の方々は、皇居「春秋の間」において天皇陛下に拝謁されました。<嶋田 亘 氏 略歴>昭和16年12月25日生、昭和39年3月・関西学院大学文学部卒業、昭和39年3月・布施螺子工業㈱入社、昭和48年2月・取締役、昭和51年3月・㈱フセラシ(同改称)取締役、昭和51年4月・同代表取締役副社長、昭和53年10月・同代表取締役社長、平成19年12月・同代表取締役会長、平成21年12月・同取締役会長、現在に至る。昭和52年6月・㈳日本ねじ工業協会常任理事、平成7年6月・同副会長、現在に至る。さらに平成15年6月~平成23年5月まで同関西支部長を歴任。昭和58年6月日本ねじ研究協会理事、現在に至る。平成9年6月・東大阪商工会議所副会頭、平成22年4月・同会頭、現在に至る。平成7年11月~平成11年6月まで通商産業省中小企業近代化審議会専門委員を歴任。平成15年3月~平成20年3月まで㈶日本品質保証機構JIS公示検査諮問委員会委員を歴任。昭和62年5月~平成7年5月まで並びに平成11年5月~平成14年5月まで近畿精密ネジ工業協同組合副理事長歴任。平成19年11月・大阪府知事表彰(業界振興と大阪府産業発展に尽力した功績)、平成22年11月・経済産業大臣表彰(業界発展に尽くした功績)
- 西精工株式会社 代表取締役社長 西 泰宏氏
-
「トップに聞く」
西精工株式会社
代表取締役社長 西 泰宏氏
聞き手 未来開発・パブリシティ委員会「トップに聞く」グループ
【インタビューサマリー】
- 会社概要 -西 泰宏 (にし やすひろ)1963年、徳島市に生まれる。1988年、神奈川大学を卒業。都内広告代理店の営業職を経て、1998年、西精工株式会社に入社。2006年、同社代表取締役専務に就任。2008年、同社代表取締役社長に就任。「かさばらないナット」で、株式会社化から規模を拡大―― 創業は1923年(大正12年)だそうですね。どのような経緯でナットを作るようになったのでしょうか。西 私の祖父である西卯次八が西製作所を創業しました。最初は家族経営で、戦時中は戦争に必要なものを作っていたのだと思います。ナットや割ピンの製造を開始したのは戦後、1947年のことです。なぜナットだったのかという背景には、四国という地理的な事情があります。今でこそ本州と橋で繋がっていますが、昔は物流を考えるとかさばらないものを作らないとだめだという判断だったのでしょう。ボルトかナットかだったら、ナット。かさばらないし、いろいろな機能も出せるのではないかということで、自然に移行していったのだと思います。―― 1960年に株式会社にされました。西 規模を拡大していこうということで株式会社にし、創業者は会長になりました。ここで創業者の息子、三兄弟が会社に集まり、初代社長には長男の幸信が就任しました。次男の輝行は1985年に2代目に、三男の佳昭 ―私の父で、幸信とは親子ぐらいの年齢差があります― は、1995年に3代目の社長となりました。幸信と輝行は亡くなりましたが、佳昭は現在相談役です。2006年に社長に就任した和彦は、長男の息子で長く専務をやっていました。今は代表権付きの会長です。―― 幸信氏、輝行氏、佳昭氏の三兄弟はどのような方々ですか?西 長男の幸信は、創業のころから祖父と一緒に作っていた現場の人です。自分で設計して、割ピンの機械も作りました。その機械は今、石井工場に保管してあります。現在割ピンは作っていませんが、ここから始まったので、ずっと置いておかなければいけないものだと思っています。次男の輝行は機械が好きな人で、自分で買いに行っていました。ドイツまで行って、これからはフォーマーの時代だと買ってきたのも輝行です。彼がいたから機械をいろいろ買い足してきたのだと思います。三男の佳昭は、「何でもした」と本人が言っています。三男坊ですから、結構きつかったのではないかと思いますね。営業でも九州や、名古屋まで出向いて、電話帳で「ねじ」を探して行ったそうです。何度か組合が立ち上がろうとしたのを、「ウチみたいなところで組合つくってどうするんだ」と諭したのも佳昭だそうです。―― 1970年に石井工場、1989年に土成工場、そして2001年、2008年にそれぞれ土成第二、第三工場と拡張されていますね。西 徳島県徳島市南矢三町の本社工場では、酸洗い伸線という材料加工をやっていたのですが、手狭になっていました。ちょうど廃業した工場のいい物件があったので、そこを改修して始めたのが石井工場(徳島県名西郡石井町)です。本社工場のまわりは、だんだん住宅地化してきました。隣には中学校ができ、病院も建ち、大きな音が出し難くなって、メインの工場をどこかに移さなければ厳しい状況になりました。そこで土成工場(徳島県阿波市土成町)を建て、その後同じ敷地内に、第二、第三と増やしてきました。石井工場も最初は畑の真ん中だったのですが、病院などに囲まれてきました。酸を扱っていますので、今は土成第三工場に酸洗い伸線を持ってきています。―― 自動車、家電、建設機械、ホビーと、幅広く展開していますね。西 皆さん一緒だと思うのですが、大阪に近いこともあり、最初はほとんど電機でした。電機自体が海外で作られるようになってきたので、自然に自動車の比率を高めていきました。いろいろなことをやっていますが、現在、自動車関連が売り上げの70~80%です。土成工場全景「創業の精神」に大切なものがあった―― 社長自身は1998年に徳島に戻って入社されましたが、当時の会社はどのような感じでしたか。西 会社がとても暗い雰囲気でした。挨拶もあまりしない、ごみが落ちている、自分たちが作った製品も落ちている、楽しくなさそうに仕事をしているという状態で、私が戻る1ヶ月前には重大事故もありました。こういう雰囲気だから事故が起きるのだろうと感じたし、私自身は東京で楽しく仕事をしていたので、考え方ひとつでどうにでもなるのになと思いました。とりあえず挨拶運動をしたり、5S運動をしたりしました。何人かついてきてくれて、徐々に変わってはいきますが、本質的には良くならない。なかなか自分が描いたイメージどおりにならないので、きついですよね。もちろん反発する人もいましたから、朝早く来ようと言うとサービス残業だと言われたり、毎日5時3分にタイムカードを押して帰る人がいたり。でも、何より私自身が精神的に追い込まれていて、夢の中でも「どうして分かってくれないの?」って思っていました。本質的に良くならない状況の中で、いろいろな良い企業を見たり、本を読んだりしました。―― 2006年に「経営理念」を制定されました。西 たまたま「盛和塾」に入って、稲盛さんの指導を仰いでいるなかで、あるとき腹に落ちたんです。「理念」がちゃんとしていなかった、一番重要な部分が欠けていたと。やっぱり「何のために」ということがちゃんと分かっていなかったら、やらされ感いっぱいになるだろうねと。それで1年かけて考えて「経営理念」を制定しました。作ってからは、まず自分が実践しなくちゃいけないと思いました。僕の理念は何だろう、経営って何だろうと考え、社員の幸せを追求するのが経営だと思ったので、とにかく社員を好きになって、社員の幸せになることは何でもやろうと。それからは感性的な悩みは消えていきました。理念の次には具体的なビジョンを作らなければいけないと思って、2009年に「経営ビジョン」を定めました。―― 経営ビジョンで謳っている「ファインパーツ」とは?西 ファイン(fine)には、優れているとか品質が良いという意味のほかに、小さい、繊細という意味もあるので、高精度、高品質、極小を表現しています。弊社で作っているナットは、1ミリから16ミリまでの小さいものです。そもそもの理由はかさばらないことなのですが、ナットは機能を持たせやすいとも聞いています。だから広がる可能性があるし、差別化もできると思います。―― 同年末に制定された「行動指針」が、理念を最も具体化しているということでしょうか。西 実はその下に、幼稚園生に言うような恥ずかしいものがあります。たとえば「誰にでも挨拶をする」とか、「はいと返事をする」とか、「いただきます、ごちそうさまをきちん言う」とか。人様にお見せするようなものでありませんが、社員手帳には「行動規範」として書いてあります。主要製品―― 2010年には「創業の精神」を制定されました。一番最近ですが、なぜこの時期だったのでしょう。西 私は会社のことを全然知らずに東京から戻って、その私が今社長をしているのですから、一度会社の歴史をひも解かなければいけないなと、ずっと思っていました。とにかく「前へ、前へ」ばかり考えていたのですが、このままではいつか大変なことになるだろうなと。不易流行ですよ。変えていかなければいけないものはいっぱいあるけれども、変えてはいけないものもある。父と2泊3日の合宿をして、「創業の精神」を作り上げました。作業としては父に思い出してもらうことばかりでしたけれどね。実はこれができてから、40年以上前の社是、社訓を捨てました。「良品を、より安く、より早く」って、今とは合わない。作れば売れるという大量生産の社是、社訓だったんです。「みんなで築く明るい職場」って、今は職場じゃない、僕たち地域を良くするんだよね、なんかちっちゃいよねって。違和感があったので。―― 創業の時点で、普遍的な大切なことがあったということでしょうか。西 「創業の精神」に、捨ててはいけないものがあったのです。これを大切にしていけば、これからも潰れることなくやっていけるだろうと。これが全ての根っこです。「創業の精神」と「経営理念」がセットでなければだめだと、そこからビジョンや戦略にいかないとだめなのだと思うんですよね。毎朝50分の朝礼で「理念」を腹に落とす―― 会社が変化していくと、合わない人もいたのではないでしょうか。西 合わない人は辞めていきました。でもある人に、普通はもっと辞めるものだと言われました。ただ今の今まで、いて欲しいと思う人はみんないてくれている。理念に合っている人がほとんどなので、思いが強くなっていきますよね。ベクトルは合っていると思います。結果的にどういうことが起こるかというと、8時10分始業なのに、リーダークラスはみんな6時半までには会社に来ますし、一番遅い人でも7時半には来ています。早く来て何をするかというと、ミーティングをしたり掃除をしたりで、機械は動かしません。―― なぜ自主的に早く来るようになったのでしょう。西 仕組みですね。「役に立っている」感を出し、必要とされてうれしいと思えるような仕組みづくりです。一番効くのが「ミッションステートメント」です。自分は何のためにここで仕事をしているのかを、私が講師になって、2年間かけて勉強して作りあげました。自分が何のために生き、働いているのかということと、会社の理念が串刺しになっているのです。―― 理念をきちんと理解してもらうためにどのようなことをしてきましたか。西 弊社には「西精工フィロソフィー」というものがあります。私から社員に毎日送ったメッセージと、それに対する返事の対話集で、200ページほどあります。対話の内容は、たとえば創業の精神の中の「大家族主義」とはこういうことだよと、朝6時15分ごろにメッセージを送る。パソコンを持っている社員が80人いますから、80人からその日のうちに返事がくる。そうですよねとか、こういう考えでいいんですかとかね。その80の返事を私が見て、次の朝にそれにつながるメッセージを送る。また80人から返事が来る。これをだいたい1週間ぐらい続けると、そのテーマについてみんなが納得して、次のテーマに移る。一方的に言って終わりというのはよくあると思いますが、弊社がやってきたのは対話です。それを経営理念制定から3~4年続けました。まだ言葉が熟していませんが、あと3~4年したら製本できるかなと思っています。今は、毎朝50分間、部署ごとに、自ら考える朝礼をしています。全体の連絡事項などが終わるとフィロソフィータイムです。「西精工フィロソフィー」を使って4~5人ずつのグループで話しをし、最後に各グループから一人が発表します。これで理念を腹に落としていきます。私は毎日いろいろな部署の朝礼に出て聞いていますが、あちこちで大笑いしていますよ。とにかく明るいことが重要。去年NHKが取材に来たときに朝礼を見て、笑っている朝礼を始めて見たと、カメラマンもディレクターも言っていました。―― 朝礼はコミュニケーションスキルにも効果がありそうですね。西 何の役職もついていない若い女性でも、公の場で言葉を求められれば、それが突然でもきちんとしゃべります。見ている人は信じられないと言いますよ。経済産業省の方も、僕だってしゃべれないと言っていました。普段から考えて発言することを練習しているからできるのです。時間内にできる製品の数だけが生産性ではない―― 朝礼の間、機械は動いているのですが?西 自動化していない機械は止まっています。おそらくこれは、どこの会社も真似できないでしょう。会長や相談役は、「もう少し短くしたら」といいますよ。でも、雰囲気とかチームワークとか、勝手には良くならない。覚悟ですよ。生産管理の課長に聞いたら、むしろ生産性は上がっているそうです。自動化できる機械は社員が自主的に考えて自動化し始めました。会社がしなさいと言わなくてもね。チームワークがよくなるので、自然と他の人を手伝ったりすることもできるようになります。「生産性」は何かというと、付加価値の生産性かなと思います。時間内にできてくる製品の数だけが生産性ではないんだなと。―― 確かに雰囲気も明るいし、みなさん気持ちのいい挨拶をしてくださいますね。西 挨拶をしたくなるような話、挨拶を続けていたらどんな奇跡が起こったかという話をしてあげるのです。弊社に置いてある自動販売機にジュースを入れ替えに来てくれる人がいますが、彼が言っていました。「僕は徳島県内全部に行くけれども、社員全員が挨拶してくれるのはここだけ。だからここには来たい」と。石油会社の、オイルを入れ替えてくれる人も同じようなことを言って、「ここに就職したいんですけど募集していませんか」って。こういう話を社員に聞かせてあげるのです。うちの社員は、会社に入ってくる方は全員お客様だと思っていますから、見学の学生にも同じように挨拶しますよ。本社屋 社員の皆さんと一緒に―― お客様の反応も、皆さんに伝えているのでしょうか。西 お客様に褒められたことや叱られたことは、現場まで全員知っています。出張報告書も、以前は部課長しか見ていませんでしたが、今は全員見ています。結果、社員満足度調査をすると、お客様のことを理解しているかとか、会社方針を理解しているかなどのポイントが上がってきます。昔は自分たちで作ったものが落ちていた。でも自分たちの作ったものが、誰に届いて誰が喜んでいるとか、誰が怒っているとかが分かったら、落としたままにはしておかなくなります。謝りに行くときは、現場の人も一緒に行くし、出張も営業と現場が一緒に行きます。お客様に会えば、現実は厳しいということも分かりますからね。「給与以上のものをもらっている」―― 勉強会をたくさん行っていると聞いています。西 とても多いですね。企業内大学で、テーマによって私や社員が講師になって、勉強会を行います。みんな熱心に参加していますね。2012年には、勉強会の取り組みが評価されて「企業人材育成大賞」をいただきました。―― 「小集団活動」も続けていますね。西 昔はあまり根付いていなかったのですが、今は根付かせるような仕組みを作ってやっています。活動は、基本的には3ヶ月に1テーマで、毎月全体朝礼のあとで1グループが発表します。年末には5グループが発表して金賞、銀賞を決めています。―― 「マイスター」制度もあるそうですね。西 もうすぐ最初の認定ですが、制度の準備はずっと前からしていました。ネジ製造技術の知識と技術をテストし、機器保全関係の国家資格や、チームワークができる人間性などを総合的な人間力を見ます。今後も毎年数人を認定していく予定です。―― 社員の評価はどのように行っていますか。西 役割評価とスキル評価、それに成果を少し加味しています。成果は、新製品の数などは考慮しますが、売り上げ、利益は加味しません。売り上げ、利益を第一目標にしたら戦略が変わってしまいます。役割表は、リーダシップとかチームワークとか、それぞれレベルが5まであります。スキル表は、営業ならここまでの見積もりができるとか、現場ならこの機械が一人で動かせるとか、ずらっと評価項目があります。その役割表とスキル表のポイントを足したら給料になる。単純明快です。さらに評価に対する「物言い」が社長に対してできますから、他の会社に比べると評価に対する不満が極端に少ないです。スキル表は張り出していますし、他の人の評価も分かります。―― 自分の評価が他の人に見られることには、抵抗を感じるのではありませんか。西 教育があるという前提ですから、あまりそういう話にはなりませんね。どちらかというと、あの人のようになりたいというほうが強いのだと思います。上を見て、もっとこうなりたいという方向に使ってくれています。―― 社員満足度調査を行っているそうですが。西 かなり徹底的にやっています。「総合的に考えると当社の社員として満足しているか」という質問があるのですが、「非常にそう思う」、「そう思う」を足すと95.9%です。見学に来られる団体や会社があると、私も話しますが、社員にも話してもらいます。社員が話をすると私自身も勉強になることがあります。先日は、来訪者から「給与について満足していますか」という質問がありました。対応した社員は、「高いか低いかといったらよく分からないが、給与以上のものをもらっている、ほかの会社ではもらえないものをもらっているので満足している」と答えていました。やはり、いろいろな「仕組み」のおかげだと思います。あとは、私の言葉を噛み砕いて実践してくれる、係長クラスのおかげです。社会貢献は利益が出ないときでもやる―― 地域の活動にも熱心に取り組んでいますね。西 経営理念を作ってから、それを血肉化しなければいけないので、ご近所のお掃除を毎日30分やっています。弊社には、社内イベントを主催する「C&C」というチームがあります。徳島マラソン、年に1回のバザー、年2回の全員でやる清掃やバーベキューなどを仕切ってくれる人たちで、毎年メンバーが代わります。リーダーには、一番向いていなさそうな人を選んでいたのですが、今は素晴らしいはたらきをしてくれています。―― なぜ社会貢献なのでしょう。西 私は徳島が嫌いで、こんな田舎はイヤだと思って東京に行ったので、その反動でしょうね。東京で17年間楽しく過ごして帰ってきたとき、こんなことをしていたら僕はきっと不幸になるなと思いました。地域に感謝して、ちゃんと返していかなければいけないという思いです。私はいろいろな会社を見に行きましたが、いい会社、社員がいきいき働いている会社は、仕事以外にものすごく社会貢献をしているのです。見学先で「儲かったらするのではない、同時にするんだ。利益が出てないときでもやるんだ」と言われて、ガツンときたことがあります。社員旅行だって、儲かったからじゃない、大切だと思うからやるんだと。利益が出たから貢献をするのではなくて、同時にやらないといけないのです。災害時の義援金なども、どこかの部署がやりたいと手をあげると、みんなが協力します。―― 定年後の雇用や障がい者雇用にも取り組んでいますね。西 定年後は本人の希望があれば、1年契約で再雇用します。現在社員の平均年齢は39歳ぐらいで、67歳という方もいます。障がい者は、毎年一人ずつ入ってきていますが、おかげで雰囲気が良くなります。難しい勉強会にも、知的障害を持っている人もまわりがフォローしながら一緒に参加します。障がい者の数、パーセンテージも大切かもしれませんが、弊社は「10分の10」を目指したいのです。雇った人が、全員幸せと思えるようにしたい。いる人が幸せでなければ意味がないので、急激には数を増やそうとは思いません。なぜならとても時間がかかるからです。まわりがフォローする、フォローしているまわりが一番成長させてもらうという、良い循環にしたいからです。―― 子育て支援の「くるみんマーク」も取得しています。西 育児休暇の社員がいると、休暇の間はまわりの社員が埋めてくれるので、100%職場に復帰します。最近は男性も育児休暇をとるようになってきました。―― このように人を大切にする経営が第三者にも評価されていますね。西 私たちの会社は四国でどのくらいのレベルにいるんだろうねと、2012年、「第1回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」に応募し、「中小企業基盤整備機構 四国支部長賞」に選ばれました。先ほどメールで、「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」の「中小企業庁長官賞」を受賞したと連絡をもらいました。「四国」には応募しましたが、「日本」はおこがましいと思って応募するつもりはなかったのですが、法政大学大学院の坂本(坂本光司教授)ゼミの方が勉強しにきて、私の講演と工場を見て推薦してくれました。坂本教授は「日本でいちばん大切にしたい会社」という本を3冊出版しておられて、良い会社を紹介しています。私たちも11冊目ぐらいに載ったらいいねと話していたんですよ。3月22日に行われた、「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式の様子強みを伸ばすように投資する―― 製品の種類は増加の傾向でしょうか。西 私が戻ってからは、むしろやめたことのほうが多いです。もともとベアリングの仕事が2割強あったのですが、今は多少残っているだけです。お客様が喜んで買ってくれていない、お客様がビジョンを持っていないのです。お客様が嫌々やっているのに、うちの社員に作ってもらうわけにはいきません。―― 設備投資についてはいかがですか。西 工場については、今後も15ヵ年計画でいろいろなことを考えています。本社工場は築40年で、補強はしていますが、つぎはぎの状態なので環境として働きにくい。最終的には、本社はネジ立てと物流ぐらいになるかなと考えています。機械は、昔はキャパが足りないと買っていました。今でもそういう風潮はありますが、「強み」かどうかで買いなさいと言っています。うちの会社がそこが得意で、そこを伸ばしたいというのであれば買いなさい、売りたいというものに絞ってやっていきなさいと。ナイロンナットのかしめ機は自分たちで作りました。―― 得意なこと、強みは何だと思いますか。西 機能性ナットでしょうね。ゆるみどめとかかしめ系とかインサート系などの特殊ナットです。特殊素材も得意です。たとえば、ベア鋼をフォーマーで打てるのは強みですね。真似をしたら機械が壊れます。経験があるからできることです。ベアリングの仕事をしていたので、自然と強みになっていきました。―― 販路の拡大、海外進出についてはどのようにお考えですか。西 弊社の製品は、お客様を通じて海外で使われています。ですから営業は海外にも出向きますが、海外に工場を建てるなどは、まったく考えていません。販路は展示会などで広げたいという気持ちはありますが、まず今のお客様を大事にすることが前提ですね。―― 今後の事業展開についてお聞かせください。西 まずは目の前のものづくりをしっかり守っていかなければいけないと思います。何か特別なことをするのではなく基本をしっかり守っていくということです。製品については、コストダウン、コストダウンで作るような製品はやめていくと思います。お互いイヤですからね。お客様が利益を取れるようにしていきたいです。それから、今後は一緒にやっていけるビジネスパートナーを広げていきたいですね。それぞれにそこでしか出来ない技術を持っていたら、それを組み合わせれば、たいがい真似できないものになると思います。誰にも負けない努力をする―― 社長ご自身についてお聞きします。どんな学生時代でしたか。西 ラグビーをずっとやっていて、高校生のときは花園にも行きました。同志社大学にはラグビーで行かれるラインがあったので、花園で1回戦に勝ったら同志社でいいかなと思っていました。でも、1回戦で55対3で負けちゃったんです。これは大学でラグビーできるレベルではないよねと思って、素直に浪人して、東京に行きました。徳島から東京に行ったら、めちゃくちゃ楽しいじゃないですか。僕があこがれている世界って、音楽と映画なんですよ。東京なら毎日、どこかで映画やっているし、コンサートもあるし、浪人生なのに居酒屋でバイトして、お酒代と映画代を稼いでいました。そんな生活をしていたので案の定、二浪ですよ。大学は神奈川大学に行きました。浪人1年目は浪人ハウスみたいなぼろぼろのところでしたが、それでも楽しかったですね。2年目は一人暮らしで、これがまた楽しくてね。でも、今でも3月ごろになると「世界史が間に合わない!」って、夢を見ますよ。ラグビーをやっている夢と浪人の夢は今でも見ますね。―― 卒業後はどのような仕事に就きましたか。西 広告代理店に入って11年間、営業をしていました。好きな映画とか音楽にも関われましたし、割とイメージどおりの仕事をしていました。―― 徳島に戻られたきっかけは何でしょう。西 次男輝行の息子、私のいとこが亡くなったことです。そのころ、私はあまりものづくりを自分がするというイメージがなかったのです。親はいずれ帰ってこいと言っていましたが、私は三男の息子ですから、帰りたくないなと思っていました。家で何を作っているのかもよく知りませんでしたね。ベアリングと割ピンを作っているらしいことだけ知っていました。食品などを送ってくれる段ボール箱に「割ピン」と書いてあったので、これを作っているんだろうな、何に使うんだろうなと。ベアリングも全部作っていると思っていたので、部品しか作っていないことは、会社に入ってから知りました。―― 帰ってくるように言われたときはどう思いましたか。西 運命かなと思いました。これに従わなかったら大変なことになる、それまで好き勝手なことをしてきたので、ここは帰らないといけないなと。楽しくやっていた営業の仕事も11年も経つと、今度は管理職で数字ばかりですよ。どんな仕事も現場が楽しいじゃないですか。辞めるにはいい機会かなというのもありました。それで戻ってきたのが1998年、ちょうど10年後の2008年に社長になりました。よく最近、「なんでそこまでやるんですか」と言われるのですが、それは昔、悪かったからです。親の気持ちも考えずにね。親がいきなり浪人の時の部屋に来て私の生活を見たときに、「あなた!いったい自分が何か分かってるんですか!」って言われたのを、今でも覚えています。そんな人間がいきなり経営者になるのですから、考え方や行動を律しないと社員さんはついてきてくれません。―― 座右の銘は?西 「誰にも負けない努力をする」です。盛和塾の稲盛さんの「稲盛経営12ヶ条」のうちの一つです。―― 趣味は?西 体を動かすこと。とにかくじっとしているのが大嫌いです。先日も17年ぶりにスキーをしました。ラグビーは年末に1回やりましたが、死にそうでしたね。1度だけ本気でタックルに行ったのですが、吹っ飛びました。フルマラソンはずっとやっています。今年は2回走ります。2月には海部川風流マラソンを走りました。会社でも毎年徳島マラソンに出ます。最初参加した社員は8人でしたが、今では80人も走りますよ。―― 最後に協会に対するご意見、ご要望をお聞かせください。西 協会の理念とか指針が欲しいですね。分科会とか委員会、教育などがありますが、それぞれに良くなっても、ものづくりを残そうというところで繋がらないのではないかと思います。基本的に日本のものづくりをこうしたい、今年の方針はこうするというのがあって、そこに活動があるという風にしたいですね。―― 貴重なお話をありがとうございました。西精工株式会社 ホームページ: http://www.nishi-seiko.co.jp/――――――――――【会社概要】創業 1923年4月 (西製作所)設立 1960年8月 (西精工株式会社)代表者 代表取締役社長 西 泰宏資本金 3000万円売上高 48億6000万円 (平成24年7月期)従業員数 238名 (2013年3月時点、同4月8名入社予定)事業内容 ナット類を中心としたファインパーツの製造・販売所在地 本社:〒770-0005 徳島市南矢三町1丁目11-4石井工場 :〒779-3233 徳島県名西郡石井町石井字石井398-4土成工場 :〒771-1506 徳島県阿波市土成町土成字大法寺240-3創業の精神一.人間尊重の精神○ 人間尊重の経営で、人と人とのふれあいと絆を大切にした、明るく活気のある会社を創りたい。一.お役立ちの精神○ 独自の技術開発力とサービスで、カスタマイズされた製品を提供し、お客様の価値を創造したい。一.相互信頼関係の精神○ お客様とお取引先との信頼関係を丁寧に築きあげて、相互繁栄をはかりたい。一.堅実経営の精神○ 身の丈に合った堅実経営で、会社を末長く存続・発展させて、地域社会に貢献したい。一.家族愛の精神○ 社員は一番大事な家族と一緒、大家族主義で社員の幸せを追求したい。経営理念「ものづくりを通じてみんなが物心共に豊かになり人々の幸福・社会の発展に貢献すること」不断の努力を重ね常にお客様に喜ばれる製品やサービスを開発し市場に供給することを通じ社会に貢献していきます経済的な安定や豊かさだけでなく自己の成長を通じて生きがいや働きがいといった「心の豊かさ」を求めていきます経営ビジョン人づくりを基点に徳島から世界へファインパーツの極みを発信する行動指針一生懸命働くこと、感謝の心を忘れないこと、善き思い・正しい行いに努めること、素直な反省心でいつも自分を律すること、日々の暮らしの中で心を磨き、人格を高め続けること――――――――――左から 池田夏来さん、勝亦良彰さん、西泰宏社長を挟んで、川端康弘さん、中江良一さん - ねじの常識、非常識 #1
-
Q:石膏ボードに直接、タオル掛けをタッピンねじで留めたがすぐに取れてしまう。
ねじの選び方または、石膏ボードの問題でしょうか?
A:石膏ボードに直接、タッピンねじで物を固定することは推奨しません。
石膏ボード用の特殊なアンカーがあり、これを使うことにより脱落を防止することができます。
まず、石膏ボードの説明をしましょう。石膏ボードまたはプラスターボードは、石膏を
主成分とした素材を板状にして、特殊な板紙で包んだ建築材料です。
安価で丈夫であり、断熱・遮音性に優れ、室内の壁・天井に最も多く使われている
建築材料で、ペイント塗装、クロス張り仕上げの下地材として、住宅・学校・ビルなどの
壁・天井の内装に使われます。石膏ボードの中には「シックハウス症候群」の原因と
なっているホルムアルデヒドを吸収し、分解する機能を持つ物もあります。ところで、石膏ボード用のねじについては一般社団法人石膏ボード工業会によると、
JIS B112 十字穴付木ねじとJIS B1125 ドリリングタッピンねじが推奨されていてどちらも、
めねじを成形しながら物を固定するものです。
しかし、これは石膏ボードを施工するためのねじであり、石膏ボードの壁に何かを取り
付けるためのものではありません。次に、なぜ脱落してしまうのかを説明しましょう。石膏ボードには結晶水が約21%相当
含まれており、これが耐火性に大きく寄与しています。しかしながら、簡単にいえば、
水分を含んだ物を板紙で包んだだけの物であるため、逆にもろい物でもあります。
そのため、十字穴付木ねじやドリリングタッピンねじを使うと石膏ボードの組織を破壊し
ボロボロになってしまい、保持力が得られないため、ねじが抜けて留めた物が取れて
しまうのです。これは、石膏ボードに直接ねじで締め付けを行った場合であり、石膏ボードの下地が
木材の場合は、木材で摩擦抵抗が得られるため、脱落はしません。問題ある施工事例
最後に、脱落を防止するために次のようなアイテム(アンカー)がありますので
参考にして下さい。1)石膏ボード用アンカー(樹脂ねじタイプ)
2)ボードアンカー
3)トグルアンカー
使用事例は写真のとおりで、このようなアンカー類を使用することにより
石膏ボードのねじ脱落を防ぐことが容易になります。従って、石膏ボードにタッピンねじで留めたタオル掛けがすぐに取れて
しまったのは、ねじの選び方の問題ではなく、石膏ボードの特性を考えた
アンカーを使用しなかったことによるものなのです。- 石膏ボードの特性を考えたアンカー -
1) アンカー(樹脂ねじタイプ) 施工後
2) ボードアンカー 施工後(裏側)
3) トグルアンカー 施工後(裏側)
- 祝! 西精工様、「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」受賞
-
未来開発パブリシティ委員会「トップに聞く」担当チームからの投稿がありました。
----------------------------
祝! 西精工様、「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」受賞
西精工株式会社様が、法政大学大学院中小企業経営革新研究所、日刊工業新聞社、あさ出版主催 「第3回 日本でいちばん大切にしたい会社大賞」の「中小企業庁長官賞」を受賞しました。代表取締役社長 西泰宏氏は、会報ねじの「トップに聞く」の取材中に、うれしい第一報を受け取りました。
贈賞式は2013年3月22日(金)に、法政大学市ヶ谷キャンパス・さったホール(東京都千代田区)で開催されます。
同社は2012年3月、四国地域イノベーション創出協議会主催 「第1回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」でも、「中小企業基盤整備機構四国支部長賞」を受賞しています。法政大学大学院、坂本(坂本光司教授)ゼミの皆さんの推薦を受け、全国版の「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」に応募し、今回の受賞となりました。
受賞企業の一報を伝えるホームページでは、西精工様について「人を大切にする経営を基本目的にしている会社で、従業員数が200名を超えた今日でも、ぶれず大家族的経営を貫いている」と紹介されています。
■「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」について
「人を幸せにしていれば結果的に業績も上がるはず。そんな大切な会社を1社でも増やしたい」とスタートしたこの顕彰制度では、「人を幸せにする経営」の実践が書類および現地視察により審査されます。「人」とは、「1従業員とその家族、2外注先・仕入先、3顧客、4地域社会、5株主の5者」を指すとしており、以下のように厳しい応募資格を定めています。
【応募資格】
過去5年以上にわたって、以下の5つの条件に該当していることとします。
1. 人員整理、会社都合による解雇をしていないこと(東日本大震災等の自然災害の場合を除く)
2. 下請企業、仕入先企業へのコストダウンを強制していないこと
3. 障害者雇用率は法定雇用率以上であること(2013年4月から常勤雇用50人以上の企業は、2.0%〈現行1.8%〉に引き上げられる予定です)
4. 黒字経営(経常利益)であること(一過性の赤字を除く)
5. 重大な労働災害がないこと(東日本大震災等の自然災害の場合を除く)
坂本光司教授はホームページに掲載されたインタビューの中で、「私は、従業員とその家族、外注先・仕入れ先、顧客、地域社会、株主『5者』を幸せにする正しい経営をしていれば、おのずと業績はついてくると信じています。(中略)厳しい時代だからこそ、5者に対する使命を果たして本当の活力を生み出すべきだと思います」と述べています。
3月22日(金)の贈賞式では、表彰および坂本光司審査委員長による講評のあと、受賞企業による講演も予定されています。一般に公開(事前登録制)されておりますので、お時間の都合のつく方は参加してみてはいかがでしょうか。
日本でいちばん大切にしたい会社大賞
http://www.taisetu-taisyo.com/index.html
法政大学ニュースリリース
http://www.hosei.ac.jp/NEWS/newsrelease/130308.html
四国でいちばん大切にしたい会社大賞
- 私の趣味は魚つり
-
三喜鋲螺株式会社、福井和廣様からの投稿です。
社会人となり、友人や先輩たちから誘われるままに様々な事にチャレンジしましたが、不惑を過ぎても続いているのが"釣り"です。釣りの愛好者は多くおられ、渓流から湖、波止場から磯と、多種多様な釣りを楽しまれておられ、私も誘われるままに何でも付き合ってはいますが、私が自分流に一番好きなスタイルは、ゴムボートに乗って海に漕ぎ出で、一人で釣るというものです。二人乗りのゴムボートに、釣り竿、クーラーボックス、アンカーと食料を積み込み、早朝、日の出とともに砂浜から沖に出かけます。初夏にはキス、冬はカレイがお目当てで、岸からの投げ釣りと同じ獲物ながら、ボートからだとやはり大物に出会う機会が増えます。また、筏釣りやカセ釣り(船頭さんにボートでポイントまで連れて行ってもらう釣り)よりも、自分の実力で広くポイントを探ることができ、努力と工夫の余地が増えるので楽しみも格段に大きくなります。通常は昼過ぎには竿を収め、陸に上がりますが、同じように沖に出ていた方々とクーラーを開けて釣果を競い合ったり情報交換をしたりと、実に子供心に戻り、何ともいえない楽しみであります。釣り人は、みんな、そうですが。子供の頃のザリガニ釣りから始まり、大和川の鮒や鯉釣り、友人との渓流釣りを経て、現在のボート釣りに至っていますが、何時の頃からか、その生き様に憧れ続けています開高健の言葉「ひと時を楽しむなら酒を飲みなさい、3日間楽しむなら結婚しなさい。一生楽しみたいなら釣りをしなさい」をしみじみと味わいながら、来週に予定している釣行のポイントを選び、獲物を想像し、仕掛けを作り、竿を磨いている最中です。写真は、先日友人に誘われた初めてのジギング(ジグという金属の疑似餌を使い、海底からジグをシャクリ上げながら魚を誘う釣り)での成果。93cmのヒラメ。 - 特殊鋼専門誌2012.11月号に「特集 ボルト・ねじ材料の動向」
-
日本ねじ工業協会 専務理事大磯義和氏が、特殊鋼誌 2012年11月号に「特集 ボルト・ねじ材料の動向」に論文を投稿しました。
今回は 「 Ⅰ.総論 -ねじ産業の最近の動向- 」です。
発行元の了解を得て「会報ねじ」に掲載いたしますので、ご活用下さい。
pdfは以下のリンクからご覧いただけます。